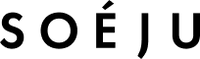Talk Live Report
SOÉJU5周年アートイベント「The Fitting Room」開催記念
これからの時代を生きる私たちとアートとの関係性
2023年10月、SOÉJU(ソージュ)設立5周年のタイミングで、ポーラミュージアムアネックスで10日間に渡って開催した「The Fitting Room」。本展を記念して、会期前日に「これからの時代を生きる私たちとアートとの関係性」をテーマに、ソージュを運営するモデラート代表の市原明日香が2人のゲストを迎え、トークライブを行いました。
ゲストには、ウィズグループ代表の奥田浩美氏と、起業家/アート思考キュレーターとして活躍する若宮和男氏。変わりゆく不確かな社会で、私たちが自分らしく心地よく生きていくために、アートはどんな役割を担いうるのか、示唆に富む鼎談となりました。
「未来がまだらに起きている」時代で思うこと
市原:まずは奥田さんから、自己紹介とアートとの出会いについてお話しいただけますでしょうか。
奥田:今日はスライドを使いながらお話ししていきたいと思います。まず、このタイトルスライドですが、これ自体が私のアート作品で、沖縄の帰りに、その(土地の)砂を使いながら描いた絵です。

投影したスライドの背景画像は、奥田さんが沖縄帰りにその土地の砂を使って描いた絵
奥田:私はいま数えただけで45くらいの役職・肩書きを持っているのですが、今日はここで、ひとつずつお話する気はありません。では、何を伝えたいかというと、肩書きによって「未来創りの仲間を集めている」ということです。すでに私たちの時代は、未来がまだらに起きていて、私は「すでに起きている未来を飛び回っている人間です」と言い切っています。5年後、10年後には当たり前になるだろうと思う行動を自分で起こすという意味で、「未来から来ました!」といつも自己紹介しています。
「無力感」だけを持ち帰ったインド留学。帰国後はITの世界へ
奥田:私は鹿児島の田舎で生まれて、22歳まで鹿児島で過ごしたのですが、初めて外の世界に飛び出したのがインドでした。22歳から25歳までムンバイ大学にいて、社会福祉の修士を出ているんですけど、インドから何を持ち帰ったかというと「無力感」だけでした。「(インドに)行く前と帰ってきた後で、何も世界は変わらなかった」という悔しさで、飛行機の中で泣きながら留学から帰ってきたという思い出があります。
その時代、私はインドでマザーテレサの研究をしていたんですが、1989年に日本に帰ってくると、すでにインドはITの国みたいなことになっていました。それなら、私がインド社会で培ったものやインド英語が生きるかもしれない。かつ、マザーテレサのようになれなくても、ITに親しんでいれば世界が早く変わるという、まさにスティーブ・ジョブズやビル・ゲイツたちが「世界を変える」と言っていたところに飛び込んだ方が、社会を変えやすいのではないかと思って、ITの世界に飛び込みました。
「スタートアップ×女性」の支援がライフワークに
奥田:そうはいっても、世界の格差は全然なくならない。地方に拠点を置いて社会実証を行うような事業もやりましたが、地方では何もスタートアップの土台がない状況でした。私が市原さんにお会いしたのは、「500 KOBE」で、私はここで初めてメンターをやりました。この時代に直面したのは、「女性がスタートアップ側にいない」という課題で、私はそこをなんとかしたいと。この「500 KOBE」もすごく意識的に女性を採択して育てるということをやっていて、7年前くらいになりますが、「スタートアップ×女性」が私のライフワークなのではないかと思いました。日本に閉じこもっていても何もできないので、シリコンバレーに合宿に連れて行ったり、インドに連れて行ったり、そんなことをやってきました。
ただ、女性の起業家がいても、なかなか資金が回りません。待っていてもどうにもならないので、自分がエンジェル投資家になって投資をしたり、あるいはLP(リミテッド・パートナーシップ)というんですけど、VC(ベンチャーキャピタル)と呼ばれる、裏でお金を出す立場で、女性の起業家をたくさん助けてきました。そして、2年前になりますが、私が投資しているAIを使ったインドの証券会社があり、そこで出た利益でインドの子どもたちにお金を出すことを始めています。実は来月、私の名前を冠して「Hiromi Vidya Foundation」という財団が立ち上がります。つまり、インドから泣きながら何もできずに帰ってきた、そこからの34年間を回収して、「私の人生がひとつの作品になった」と思う年が、今年なんです。
私の存在自体がアート的なもの
奥田:そんなわけで、人生でやってきたことはバラバラなんですが、私がこの体を使って、伝えたかったことは、「世の中に愛とか希望を増やす」ということ。私が存在することで、人の気持ちや心を動かすというのを30数年かけてやってきた。では、なぜ私はこうやって人の気持ちや心を動かせるのだろうと、自分に向かい合ってみたときに、「私の存在自体がアート的なもので、それは私に限らず全ての人にいえるのではないか」と思い至りました。たまたま今年若いアーティストに出会ったときに、「奥田さんそのものが、すでにアートの試行錯誤を終えているから、(奥田さんが)出したものはもう全部アートなんじゃないか」と言われたんですね。それならと、私が世界中を飛び回って、自分と共に世界を見て、ボコボコにされながら傷ついてきたRIMOWA(リモワ)が私らしいものかなと思って、RIMOWAを引退させるときに、そこに描いて作品にするということをやっています。

奥田さんがRIMOWAに描いたアート作品
肩書きで表現しきれないものを、アーティストという形で実践している
奥田:私がアーティストと名乗り始めたのは今年で、すでにアーティストと名乗る人からすると経歴は浅いのですが、何を表現したいかについては、ずっと30数年間人生と向き合って、あとは作品を出すだけだったと気づいたんですね。だから、どんなステージであれ、人々がそれを自分の作品として出したものには、それぞれの人の背景が反映されて、アートとアートで会話をすれば何かが見えてくるんじゃないかなと思ったんです。
そこで、私はアートとアートで会話をさせる「Soul Dialogue Gallery」という場所をつくりました。1、2週間におひとりくらいずついらっしゃっていますが、そこで何が起きるのかというと、言語の壁を感じている状態、あるいは不確かな中で、アートとアートを置くと、上手下手じゃなく、あなたってこういう内面があって、あるいはこういう未来があって、というのがわかるんですね。作品を持ってくる方々の半分くらいが起業家で、芸術家の方は少ないのですが、何か一瞬ポッと出したものを会話させる場所をつくっています。

アート同士を会話させるという「Soul Dialogue Gallery」
奥田:私はアートを始めてから、自分という存在が「まんまる」だということに気づいたんですね。そして、私だけがそうなのではなく、本来人間というのはまんまるな状態で、社会だったり家族だったり、先生が「あなたはこうするべき」と押し付けて、ぎゅうぎゅうになってしまっている。そこから脱出するために、自分を尖らせてみたり、凹んでみたりという状況がある中で、アートを通して自分がまんまるな状態ってなんだろうか、どう表現できるだろうかということに向き合っています。つまり、45以上ある私の肩書きの中で表現しきれないものを、アーティストという形でやっているというのが私の自己紹介です。
市原:今、奥田さん自体がアートなんじゃないかというお話がありましたけど、「500 KOBE」で奥田さんに初めてお会いしたときに、まず「生の奥田さんだ!」と思ったんです。まさに本物のアート作品に触れたときの感動ですよね。ご本で拝見していた時とまた違う感覚があって、奥田さんを介して自分の気づいていなかったところに気づくこともありました。
奥田:まさに私を作品のように眺める方も多くて、講演後、名刺交換の列ができるんですけど、アート作品を見るように、浴びにきたという感じの人が多いですね。でも、実はみなさんもそういう光みたいなものを中に持っていて、まんまるなものをパーンと出せば「全員がアート作品のようになるのにな」と思いながら講演をしています。

左:市原明日香 中央:奥田浩美氏 右:若宮和男氏
建築士を経て、2度目の大学でアートを研究し、新しい価値を創造する起業家へと転身
市原:次は若宮さんに、自己紹介とアートとの関係についてお話をお願いしたいと思います。
若宮:僕は1976年に青森県に生まれたのですが、当時まだまだ昭和的な価値観が多いところで。80年代、90年代初頭はサブカルの流れで、音楽とファッションに大分はまっていました。そこから建築を学び、建築の設計士としてやっていたところから、もう一度大学に行き直しました。そこで美学芸術学を学んでアートの研究をしたというのが、深くアートに関わったタイミングで、その後、大企業で新規事業に長く携わり、今は起業して2つの会社を経営しています。
そのうちのひとつ、「uni’que(ユニック)」という会社では、女性の起業家がまだまだ少ないという日本の現状があるところで、事業アイディアを持った女性と一緒に、エンジニアやデザイナーが事業の立ち上げを行い、独り立ちしていただけるようサポートする「Your(ユア)」っていうインキュベーション事業をやっています。例えば、更年期のフェムテックや手紙のサブスクとか、そんなサービスが始まっています。この会社とは別に、この4月にはメタバースの会社をつくり、日本から世界で活躍するメタバースのクリエイターを生み出すことを目的に、クリエイタープロダクションをやっていたりします。
あとは、新しい価値や新しい事業をつくるという観点で、資生堂やパナソニックなど、大企業のアドバイザーをしていたり、日経オピニオンリーダーのほか、Voicyという音声メディアでパーソナリティもやっています。

建築士のキャリアから、大学に行き直しアートを研究。その後は大企業の新規事業立ち上げから、ビジネス最前線で活躍
ブレイクスルーを起こすには、アート的なあり方も必要
僕がもともとアートの研究をしていたということと、「新規事業やイノベーション起こすぞ!」みたいな企業で長くやっていてもなかなかブレイクスルーが起きないというところが、自分の中ではつながったんですね。そこで、芸術家の価値のつくり方のような、課題解決思考にはないあり方が必要だと感じて、「アート思考」の本を出したり、現代アーティストの皆さんと、この2、3年、一緒に活動したりしてます。

2019年、2021年にアート思考に関する著書を出版
2022年夏に渋谷で「よそおうのこれから」展というのをやったんですが、メイクやファッションの価値って、今すごく変化の時期にあると思っているんですね。そもそもコロナで人と会わなくなったときに、「ファッションとかメイクの価値ってどういう風になっていくんだろう」と。「もともとは女性しかメイクしない」とか「性別で服装を分ける」みたいなところも激変していますし、それこそメタバースでは、人間じゃないものになったり、性別を超越した存在になったりということがある中で、現代アーティストやメディアアーティストの方々と一緒に、展示とワークショップを通じて、「これから”よそおう”ということはどういう風に変わってくるだろう?」 みたいなことをやったイベントです。
いろいろバラバラにやっているように思えるんですけど、”ダイバーシティ”と”クリエイティビティ”、そしてメタバースにおける”グローバル”が今3つの軸としてあって、それらは自分の中ではひとつにつながっていることでもあります。
2022年夏に渋谷でアーティストと共に「よそおうのこれから」展を開催
拡張し続ける「よそおう」の意味
市原:ありがとうございます。アートとファッションっていうところでは、今回、ソージュが主催する展覧会「The Fitting Room」のインスタレーションにおいても、ふと自分と向き合ったときに「自分と社会との接点はなんだろう」とか「自分がどうあるのが心地いいんだろう」とか、そんなことを考えていただくきっかけになれば、というのがひとつの思いとしてありました。まさに「よそおう」ということ自体の意味も拡張してきていると感じていますが、メタバースもそうですよね?
若宮:「よそおう」にはいろんな字があるんですけど、衣装の「装」でも装うだし、化粧の「粧」でも粧うになります。他には扮装の「扮」、「ふりをする」というのもそうですよね。強盗が配達員を扮って、というときも扮うです。つまり、よそおうことで「自分ではないものになる」ということなのか「自分らしくある」ということなのか、どちらにも捉えられます。展覧会の来場者に「あなたにとって『よそおう』とはどういうことですか?」と聞いたら、「武装している感じ」という人もいれば、「自分らしくある」という真逆の人もいて、結構面白かったですね。
奥田:私が今日着ているのは、ソージュさんからいただいたワンピースなんですけれども、実を言うと、ワンピースに重ねているストールは、一昨日インドに設立したNPOの記念にいただいたシルクのストールなんです。なんだか運命だなって思ったんですね。ワンピースとストールが同じ時期に私のところに来て、私はそれを今日この場で発信するんだって考えたら、アート作品をつくるのと同じように、いくつかのお洋服の中から選ばれて私のところに来たんだと。まさに、アートとファッションの掛け合わせを、私も今日表現してるんだなって思ったのですけど、逆に市原さんに質問していいですか?(ブランドを立ち上げて)初期の頃からアートにこだわってきたという、その背景を知りたいのですが。
なぜいま言葉ではなくて「アート」なのか?
市原:ありがとうございます。まさに、今日のテーマでいう「なぜ、いま」というところかなと思うんですが。社会との接点でいうと、先ほどあったように「武装のために洋服を着る」という方もいらっしゃるんですね。私自身も人生を振り返って、「どういう気持ちで洋服を着てきたかな?」というと、特に社会人になってからは「場に求められるものを着なきゃいけない」という、大げさにいうと強迫観念のようなものがあって、そこから解き放たれたいという思いがすごくあったんです。ただそれを、こっちの世界はいいけど、こっちの世界はつまらないというような二項対立にはしたくなかったんですね。「ただ心地よくなりたい」という思いを、どうしたら共感してくれる方々とセッションできるのか考えた時に、その手段って言葉じゃないんじゃないかなと思ったのが最初です。まさに「Soul Dialogue Gallery」に通じますね。
奥田:なるほど、まさに言葉じゃないという意味では、本当にいま言語というものの価値がどんどん下がっていると思っています。言葉を社会に出していこうとするなら、生成AIに任せちゃった方がたくさんの言語を吐き出してくれますから。それなら「自分らしさを表すには、究極的に何なんだろうか?」と考え始めたのが、実は私が今年になってアートを始めたきっかけでもあります。さっき45ぐらいの肩書きを見せましたけど、もう言葉による肩書きでは伝えられなくなって「アート的に私を表現するとしたらこんな感じです」とした方が伝えやすいなと感じて、今年からアートを始めています。
市原:奥田さんが今年からアートとおっしゃるのもなんとなく不思議な感じがして。私にとってはもう、奥田さんはアートだったという感じがします。
奥田:いろいろなアートフェアや美術館に行くと感じるのは、現代アーティストの方々はたくさんの作品をつくりながら、自分をどう表現するのか闘っているんだなと、20年、30年かけて試行錯誤しているのだと思いました。私の場合は起業家として、あるいは社会改革家としての歩みみたいなのがあって、これは結局、現代アーティストが「この作品が自分っぽい?」と膨大な数の作品をつくっているのと同じようなことを実体験でやってきたんじゃないかなと思って、自信を持てたんですね。私はもう30年やっているから、これでいいんじゃないかと...そんな感じですかね。

「正解がある時代じゃなくなった」とみんなが感じている
市原:(自分を)ラッピングして出すタイミングだったという感じですかね。若宮さんにとっては、最近アートとの関わりの中で、何か意味のあるタイミングと感じられることはありましたか?
若宮:2015年ぐらいから「アート思考」とか「起業家はもっとアートに触れた方がいい」と言われていますが、若干バズワードっぽくなってしまっていて、一過性になってしまうのも僕はいけないなと思っています。でも特に日本は、もうちょっとアートに触れるというか、社会とアートの接点が増えていった方がいいなと思っているので、そういう活動をしているんですけど。価値のパラダイムが、よく言われるように「正解がある時代じゃなくなった」というのはやっぱりみんな感じているところがあると思います。ビジネス界隈だけの話ではなく、アート思考のような話は、誰かが体系化したというよりも、日本に限らず、同時多発的に広がっているので、やっぱり時代的なものとしてもあるのではないでしょうか。
奥田:VUCA(ブーカ)という言葉が、 5、6年前から出てきたのと同じ流れですよね。この不確実な時代に「A or B」と問われて「Aが正しいです」と言えない場合、何か他の表現方法はないかというときに、いま、ネガティブ・ケイパビリティーという言葉も出始めてますけど、「どちらの立場でもないけれど、自分はここにいる」とか「悩んでいる自分がいる」というところにアートが寄り添えることがわかってきたっていうのが私の解釈に近いですね。
市原:アートが寄り添うという感覚って何ですかね? 少し心が弱くなってるときとか何かに悩んでるときは、アートに触れたり、自分自身で表現するタイミングなんですかね?
奥田:私はアートをやるようになってから気づいたことがあるんですが、「Soul Dialogue Gallery」でアートで対話していると、未来のビジョンを描く人もいれば、いまの自分の感情を出す人もいるんですね。(アートは)人それぞれ生きていて、どういうところに一番インパクトを受けているのかがわかりやすいし、過去や未来についても、抽象的でありながら掘り下げられるいいツールになりうると感じています。
ロジカル思考、デザイン思考、アート思考の違いとは?
若宮:僕がアートに興味を持ったのは、音楽をやっていたときで、自分は曲を作るというよりは DJ をやっている側だったんですが。でも音楽って、何で要るのかよくわからなくないですか?不要不急とかコロナで言われましたけど、なくても死なないですよね。でも詩人や音楽家という職業は、職業の中でも最古の部類に入っている。「なんで人間はアートや音楽を必要とするんだろう?」と。これに対して、僕の感覚では、世の中の常識とか社会の構造って、ひとりひとりに必ずしもフィットしていないじゃないですか。 20世紀はその社会のメッシュに無理やり自分の形を合わせてみたいなところがあったと思うんですけど、それがしんどくなったときに、アートは別の形を示してくれるのではないかと。
言葉の切り分けとして、「ロジカル思考」「デザイン思考」「アート思考」というのがありますよね。ロジカル思考は説明文みたいな感じで、大体の人にとって分かりやすい。デザイン思考はコピーライティングみたいなことで、ちょっとそこに感情がのります。アート思考は詩という感じなので、ちょっと分かりづらいけど、独特の質感がある。「こういう言葉の使い方していいんだ」とか、いわゆる常識的なルールをちょっと逸脱していくときに、ふっと楽になったりとかする部分があるのかなと思います。
分からないことに耐える力と迷走力の大切さ
奥田:「意味を考えなくても受け取っていいんだ」というのが、私はいまアートで一番強いメッセージだと思っています。日本人でアートに馴染みのない方って、このアートは何を表現しているんですか?と解説文をすごく欲しがるじゃないですか。でも大体のアーティストが「それはあなたが受け取ったままでいいです」とおっしゃるので、その受け取り方にすごく意味があるのではないかと。例えば、私という人間が活動していて、私は私なりにメッセージを出しているけれど、私から離れて、みなさんが受け取る奥田浩美の活動というのは、もはや私じゃないという意識があって、その人なりに解釈された私の意味を受け取っている。「受け取った人次第の解釈でいい」という風な心の捉え方をしないと、これだけ不確実で明日が見えない、かつ戦争もあって不安定なときに、「Aが正しいか?Bが正しいか?」ともう絶対的に言えない時代が来ちゃった。来てしまった中で、私はAともBとも言えないけれど、何かを受け取ったという、この雰囲気がいわゆるバイブスみたいなことで。「これが私の解釈で、あなたから出されたものです」というイメージを持つのが大事なんじゃないかな。
若宮:先ほどネガティブ・ケイパビリティの話も出ましたが、人間って分けたいんですね。 わかるも「分かる」と書くので、分けられると安心はするんですよ。「アートがわからない」ってみんな言うのは、分けられないものとしてあるから。アートに触れる機会が多い人の方が、わからないことに耐える力があるのかなと思います。
奥田:わからなくてもいいじゃんと。 AともBともつかないときに、どちらでもなく耐えるとか「まあ、いいかー」と思う気持ちは大事ですね。あともうひとつ、最近大事だと思うのが「迷走力」です。「ああかもしれない。こうかもしれない」と迷走しながら、正しいところがもう一生ないかもしれないというところに進んでいく力が大事だと思います。でも、その迷走力の進む過程って、言語でロジカルに示せないし、小説でもいいオチはできない。そうなら、やっぱり途中のパッションみたいな、正解はないけど、私はいまこんな感じというのを出すのが、いまでこそアートだなと。
起業は「社会彫刻」に近いのではないか?
市原:さっき未来のビジョンを表すのにアートを使われる方もいるというお話があったと思うんですけど。いま自分のこと振り返っていて、奥田さんにメンタリングしていただいた頃って、自分の中にあるマグマが何なのかはうっすら気づいてたんですけど、今のソージュのビジネスモデルを言語化できてなかったんです。「言語化できてないけど、自分の中にすごいマグマがある。とにかくそれを誰か信じてくれないかな」という時代があったのですが、そこから7 年経ってようやく最近言語化できるようになったんですね。でも「言語化できないから」と諦めてしまう人たちがいるなら、先ほどの女性の起業家支援じゃないですけど、アート的な何かがあると伴走しやすくなったりするんですかね?
若宮:ヨーゼフ・ボイスという現代アーティストが「社会彫刻」ということをいったのですね。社会を彫刻するように、何かアクションを起こしたら社会は変わるんじゃないかと。そういう意味で、彼は誰もが芸術家として社会に参画できると言っているんですが、起業はそれに近いのではないかと。
僕はアート作品を創作するのは、自分に出会い直していくプロセスだと思うんです。芸術家は先に描きたいものがあって、それをつくったと思われるかもしれないですけど、実際はつくっていく過程で変わっていくもので、多くの芸術家はできあがって初めて、自分はこれがつくりたかったんだと分かるという感じなんですよ。創作のプロセスとか、迷走力とはそういうことだと思いますし、起業家はまさしく現在の価値で観測できない価値を生み出そうとしているものですよね。
奥田:そうなんですよね。起業家は、プロダクトマーケティングフィットみたいな「これが世の中に刺さる」という仮説や実体験をもって進んで行きますけど、それももう通用しない時代が来る。時代の流れに自分たちを乗せながら、でもその中でも「失わない何か」を表現できるのがアートに近い発想なのかなと。今日揃っているのが全員起業家で、皆でアートをこれだけ喋るというのがひとつの象徴だと思います。
市原:社会彫刻という言葉、すごくいいなと思いました。ブランド設立1年目にポーラミュージアムアネックスで開催したイベントも今回も「何のために?」と聞かれると正直うまく説明できないんです。でも社会彫刻だって思うと、きっとこれを続けていくことで何かになるという勇気をもらえますよね。
アートに触発されることの可能性
若宮:触発するという概念でよく言うんですけど、ロジカル思考とかデザイン思考の場合、基本的にひとつの方向に人を連れて行くんですよ。こうしてくださいと言ったらこうなるとか、論理学は誰が考えても同じところに行けるから、パワフルなツールなんです。デザインもアフォーダンスっていう理論があって、例えば、扉があったら、押す側と引く側がわからないデザインはあまり良くないんですね。誰でもそこに立ったら「押す」って瞬間的にわかる方がいい。一方で、アートはさっき奥田さんおっしゃってたみたいに、解釈の多義性の方が大事です。でも何も仕掛けないということではなくて、奥田さんの作品なら、奥田さんの生き様が結晶化したものになって、それを見ると、人によってどう感じるかは違っても、その作品に触発はされるんですよ。どう変化するか、どっちに向かうかもわからないけれど、そういう触発の玉突きみたいなことが起こっていく。ビジネスの場合も、目的とかビジョンをもって起業しても、本当はどこに到達するかは分からない。だけどそのどこに到達するかわからない、自分との出会い直しのプロセスが、次の人に火をつけて、次の触発を生んでいくみたいなことはある。アート作品を見て自分もつくりたくなるとか、そういうリレーはされていくけれど「どうなるかはわからない」ということは、あるのかなと思っています。
課題解決思考ではいけないゾーンがある
市原:お話をうかがっていると、おふたりは結構シンクロされていますよね。
奥田:そうですね。ちょうど若宮さんが「アート思考」の本を書いていて、最後の仕上げをしているときに、私の鹿児島の合宿に来たんですね。そのとき、私はアート思考という言葉を全然知らなかったんですけど、それに近いことを実地の合宿で4日間ぐらいやってるところにシンクロして。あのとき、なんで飛び込んできたんですか?
若宮:なんででしょうね。「破壊の学校」という合宿だったんですが、僕の固定観念というか、それまで自分が思っていたものを相当破壊されたんですけど。
奥田:参加者の中で男性ひとりだったんですよ。そこに何をもって吸い寄せられてきたのかが、私はいまでもわからないんです。
若宮:奥田さんに引き寄せられたんですよ。
奥田:じゃあ私がアートだったんですね(笑)。若宮さんは、「アート思考」という本をちょうどその瞬間に書かれていましたね。
若宮:はい、まさに鹿児島で書いていましたね。
奥田:あの時代に「アート思考」について書こうと思ったのは、その前の時代に対するアンチテーゼだったのか、どういう背景だったんですか?
若宮: 自分が新規事業をずっとやってきた中で、ロジカルシンキングもデザインシンキングも一通りやったんだけど、なんかそういうことじゃないんだよね、というのがあったんですね。結局、課題解決志向だと行けないゾーンがあることがわかったんです。「バカじゃない?」と言われてもそれをやっちゃうっていうのは、もう癖みたいなもんで、やっぱりそういう自分になっていくプロセスみたいなものが、スタートアップの人は本質的にあるんだと思うんです。それは、アーティストに近いマインドで、「なんでやるんですか?」と聞かれたら、説明はできないんだけど「だってそうなっちゃうだもん」みたいな。ビジネス側は、すごくロジカルで、理由、目的、課題解決に触れすぎちゃっているので、こっち(アート)側が足りていないなということで、アート思考の話をしています。
奥田:私は最近「課題解決病」と呼んでいるんですけど、特に若い世代は、学校でも課題解決と言われて、探求学習みたいなことばかりやっていますよね。でも、もともとその課題つくったのはその子たちじゃなくて、私たちのもっと上の世代なのにと思います。課題解決から何かものを生み出すのではなく、自分の興味やワクワクするもの、まだいまの時代に全くないことでも、妄想みたいなところから入った方がいいんじゃないかという意味で、アートは限界もないし、自分がつくりたい世界に向かえる。課題解決は残しておいていいと思うんですけど、それだけじゃダメだよね、というのは私の中にあります。

アート的鑑賞方法で子どもを捉えることが大事
市原:ここで、視聴者の方のコメントを読み上げますね。
「確かにロジックだけで考えると、時代は古くなってきていますよね。アートと教育、家族関係、哲学や歴史の関係について、みなさんのオープンな取り組みをお聞きしたいです」。
これについてはどう思われますか?
奥田:教育の分野もアート的鑑賞方法で子供を捉えるのがすごく大事だなと思っています。通知表も、別にまんべんなく教科で見るよりは、「この子はここがすごい、どこか光ってるかな?」という、もうそれだけでいいんじゃないかなと思ってます。私は娘がいますけど、娘の悪いところみたいなのは、あんまり見る必要もないし、いいところという概念すらなくて、彼女には彼女としての作品があって、この作品をどこの環境に置いたら一番きれいに見えるだろうという風に、ちっちゃい頃から実は考えていました。だから、いっぱい褒められるところに娘を置いてきたんです。例えば、いまお琴をやってるんですけれども、お琴っておばあちゃんたちだらけなんですね。そこに3歳ぐらいから「師範を目指します」みたいな子供がいると、ちやほやされて。お稽古は厳しいんですけど、「あなたは、すごいすごい」と言われて育つんですね。実はうちの母から預かったお琴があり、家にそういう伝統があったという背景もあるのですが、そういう娘を作品として考えたときに、どんな光が当たる場所に置いたらいいんだろうというのは、私はずっと考えてきたんですよね。いまの質問から私が一番感じたこととしては、学校に行く行かないとかも含めて、「どこにその作品はあるべきですか?」ということですね。
市原:私も個人的に教育に関しては聞きたくなってしまうんですけれど、「どこにその作品を置くのがいいのか」を考えるのは、やっぱり親としての責任感として感じてらっしゃったんですか?
奥田:結局、愛は支配というか、自分の思い込みも激しいところもあって、ここがいいだろうと名門私立女子校に入れましたけど、そこのギャラリーが良かったかどうかは親子含めて、そのときには正解が分からないですね。結果としてすごく娘には良かったと思ってますけど、必ずしも親の見立てが合っているかどうかは、当てにならないんじゃないでしょうか。
市原:それも色々やりながらという感じでしょうか。
奥田:「この作品はどこにあるべき」というのはなくて、いろんなところに置いてあげればいいのかな。でも、そのオーナーシップを外す時期でもあるんじゃないかなと。
市原:いろんな人に鑑賞してもらって。
奥田:そう「すごい作品だね」と。人によって見方が違うというのが、ある意味いまの教育だと思います。学校の真四角な中にドンと置いたって、教室の中で光る作品はそうないですよ。
「守破離」のステップを通して学べること
市原:若宮さんは、教育に関して思うことはありますか?
若宮:本当に教育のことは色々変えていかないとなと思っているんですけど。僕がアートの話をしていると、「じゃあ、型通りの勉強は全く意味がないんですか?」と聞かれることがあるんですけど、そういうことでもないと思っているんですね。芸事で「守破離」という言い方がありますけど、最初は型を守りますということで、型通りにやる。そうして型通りにずっとやっていると、自分にとって気持ち悪いところが見つかって型を破る、守破離の「破」にいく。そして最終的には、型を離れて、「自分だけの型を見つけていく」という考え方なんです。ごく一握りの天才は、いきなり型を離れて「離」からいく人もいるかもしれないですけど、多くの方は「自分がやりたいことをやればいいんだよ」と言われても、それがわからないということがあると思うんですよね。そういうときは「最初は型通りコピーしまくってみるといいよ、どうせできないから」と。「どうせできない」というのは、人はそれぞれ違う形なので、型通りにやったら、ここが気持ち悪いなと気づくということなんですね。だから1回型通りやるのはいいと思うんですよ。
ただ勘違いしちゃいけないのは、日本の教育だと「守」が神様になっちゃって、型通りやれた人が点数がよくて、上がっていくみたいなことになってるんです。でも「守」はステップ1なだけで、これをいかに飛び出していくかということが大事なんです。1回教室に入って、みんなとやってみてもいいんですけど、そこから飛び出していったときに「あ、ステップが上がったね」という捉え方をして、最後は自分らしさを見つければいいと思うんですね。だけど、学校でも企業でも、マニュアル通りやることが神様になる。それはステップ1なのにねっていうのが考え方としてあるなと感じています。
奥田:絵画の中でいう、デッサンが大事みたいなのと一緒ですよね。結局デッサンばっかりやってるのが、今の日本だということですよね。
若宮:それは、あくまでも自分らしさを見つけていくための手段というか、1回目の便宜なだけなんですけどね。
居心地の悪さに慣れるためにも、アートに触れてみてほしい
市原:なかなか深いご質問をいただいたので、これを一晩かけて語りたい気持ちはありますが、アートと哲学、歴史との関係、家族関係...本当に全てにつながっていくところなんだろうなと思います。最後に、今日お話を聞くまで、アートを少し遠いものと感じていた方々に対して、おふたりからメッセージをいただけますでしょうか。
奥田:アートに関しては、つくる側でも鑑賞する側でもどちらでもいいので、どちらかから必ず触れてみてほしいなと思います。「どう見たらいいのか、どう解釈したらいいのか」の居心地の悪さみたいなものに慣れるためにも、表現してみるか受け取ってみるのが大切だなと思います。私のギャラリーに来て、一緒に描いてみるのもありなので、ぜひいろんなところに飛び込んでみてください。
詩のような大人が増えていけば、世の中はいい柔らかさになるのではないか
若宮:日本の大人が特にそうなんですが、アートに対して苦手意識をもつ方がめちゃくちゃ多いんですよ。「何が描いてあるかを正しく読み取らなきゃいけない」と思っているかもしれないんですけど、アートを鑑賞するときに大事なのは、自分のどこがどう反応してるかみたいなことだったり、新しい世界の捉え方に出会うことだったりするので、そういう意味で、こう見なきゃいけないというのはないので、そこを楽しめるようになると、いろんなことが楽しかったりするので。ビジネスでも人でも、僕はよくポエティックな人とか、ポエティックな事業だねという言い方をするんですよ。さっき言った言葉の使い方も、説明文もあれば、コピーライティングもあれば、詩もあるんですけど、詩のような人が増えていくと、特に大人がそうなれば、次の世代も含めて、すごくいい柔らかさになるんじゃないかなと思います。ぜひ一緒にアートを楽しんでいきましょう。
市原:おふたりとも温かいメッセージをありがとうございます。私自身もアートに敷居の高さを感じてしまうことがある人間なのですが、今回ソージュが主催させていただいたアートイベント「The Fitting Room」を通じて、私もいろんなことを感じてみたいなと思ってます。ぜひ多くの方に足を運んでいただき、何か発信していただいて、それが社会彫刻につながっていくと嬉しいなと思います。ご視聴くださった皆様、ありがとうございました!